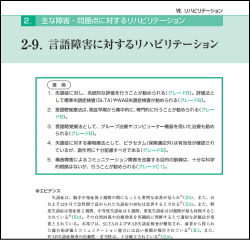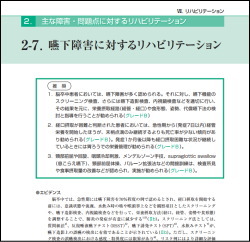脳出血の基礎知識として、脳出血とは&その症状、リハビリ(理学・作業・言語)、再発を防ぐ&病診連携、高血圧と薬、減塩食及び、痙縮と拘縮についても一通り学んでおきましょう。
脳出血(脳卒中)の基礎知識
脳出血、広くは脳卒中の基礎知識として以下(脳出血とは&その症状、リハビリ[理学・作業・言語]、高次脳機能障害、再発を防ぐ&病診連携、高血圧と薬について、減塩食について及び、用語「痙縮(けいしゅく)」「拘縮(こうしゅく)」)を掲げましたので、チェックしてみてください。
退院後の手足のケアの事など、入院中では分からないような事も載っていますので、一度ご一読するよう強くお勧めします。
基礎的な知識は、インターネット上の多くのサイトで説明されていますが、「国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス」が、一つにまとめられていて、イラストがあり、分かりやすいので本サイトでは引用させて頂いております。
又、高次脳機能障害及び、そのリハビリについても高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)を引用させて頂いております。
尚、脳出血だけではなく広く脳卒中として説明されているのがほとんどですが、脳出血は、その中の一部であることをご理解ください。
※本ページの外部リンクは、他サイトのため突然リンク切れになる場合があります。ご了承ください。
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
脳出血とは&その症状
- 脳卒中|病気について 1.脳卒中とは
- [2] 脳卒中が起こったら >昔からの言い伝えを捨てる
- [19] 脳卒中にもいろいろあります >脳卒中のさまざまなタイプ
- [114] 脳出血 最新情報と対処法 >脳出血は日本の国民病
2.脳卒中の症状
3.脳卒中を疑ったら
4.病院での検査、治療
5.脳卒中の予防
>症状は百人百様
>激しい頭痛はクモ膜下出血の疑い
>脳卒中の症状は体の片側に
>症状の起こり方は?
>発病したら、どうするか
>前触れや“警告発作”がある時
>前触れがない病変の場合も
>再発率が高いから
>どんな人が脳卒中を起こしやすいか
>死亡原因の第3位
>主な症状と徴候
>脳卒中が起こったら-その応急措置
>タイプ別の特徴
>急性期の治療
>再発を予防するには
>脳出血の原因―生活習慣と高血圧
>脳出血の症状
>脳出血の治療―すぐに救急車を
>脳出血を起こした後
>こんなときはどうする
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
リハビリ(理学・作業)
- [16] 脳卒中のリハビリテーション >脳卒中になると
- [81] 脳卒中のリハビリテーション >まず脳卒中を理解してください
- 【ブルンストロームステージ】片麻痺の評価段階を徹底解説! >ブルンストローム・ステージの目的
※リハビリを行なうに当たって非常に大事なので、必ず読んでください!
>リハビリを考える3つのポイント
1.まひは回復するか
2.訓練の効果は
3.まひに対する訓練と残った能力を開発する訓練
>急性期の訓練
>「亜急性期」(急性期のあと)の訓練
>慢性期の訓練
>QOLを高めよう
※「退院してからは・・(2)関節を硬くしないために」は、要チェック!
※長嶋茂雄氏(ミスター・ジャイアンツ)が脳梗塞になったことが紹介されています。
>リハビリテーションはだれが行うのですか?
>チーム医療の大切さ
>いつから始めるのですか?
>急性期のリハビリテーション
>理学療法の実際
・杖にはどんな種類が
・装具はどうか
>作業療法の実際
・利き手交換
・更衣動作
>急性期脳卒中の患者さんにはどのような注意が必要か
>急性期リハビリテーションのあとは
>継ぎ目のない医療
※杖と装具の種類と用途が記されていますので、要チェック!
※自分の今の症状がどのステージにあるかチェックしてリハビリの目標を設定しましょう!
>ブルンストローム・ステージの回復ステージ
>上肢のブルンストローム・ステージ
>手指のブルンストローム・ステージ
>下肢のブルンストローム・ステージ
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
リハビリ(言語)
- [15] 脳卒中と言葉の障害 >誤解されやすい病気-失語症
- [112] 脳卒中の言語リハビリテーション - 家庭で効果を上げるには - >言語障害のリハビリテーションの流れ
- [100] 元 NHKアナウンサー山川さんの脳梗塞からの生還記(主に失語症)
- 言語障害に対するリハビリテーション(脳卒中治療ガイドライン2009:日本脳卒中学会)PDF
- [83] 続・脳卒中のリハビリテーション >言葉の障害への言語聴覚療法(失語症とは?、運動障害性構音障害(麻痺性構音障害)とは?)
- ネットで学ぶ発音教室 理論編
- 嚥下障害に対するリハビリテーション(脳卒中治療ガイドライン2009:日本脳卒中学会)PDF
- 嚥下リハビリ相談窓口(日本摂食嚥下リハビリテーション学会)
>失語症とは
>失語症にいろいろなタイプ
>症状で分類すると
>運動障害性構音障害とは
>言葉の障害が起きたら
>リハビリテーション
>重要なコミュニケーションへの努力
>患者さんとの接し方-6つのポイント
>深めたい言語障害者への理解
※長嶋茂雄氏(ミスター・ジャイアンツ)が国民栄誉賞授与式でのあいさつのため、何回も練習したことが紹介されています。
>家庭でのリハビリの基本的な考え方
>失語症:家庭でできること
あいさつ、会話、書字、日記、はがき・メール、手帳・カレンダー、コミュニケーションカード・ノート、市販の教材、地域社会での交流
>失語症:気をつけたいこと
>運動障害性構音障害:家庭でできること
よい姿勢を保つ、首や肩の運動、深呼吸、口の運動、発声、発音
>運動障害性構音障害:気をつけたいこと
※最新リハビリ情報の「失語症の言語リハビリ」も参照してください。
※失語症の教材、グッズ及び、言語聴覚士のいる施設については、
>食べたり、飲んだりすることの障害への摂食・嚥下機能療法
>構音障害とは?構音発達とは?
>構音障害の種類
>誤り音の種類
>異常構音とは
>構音指導の内容
実践編
>構音指導の進め方
>耳の訓練とは
>カ行音とは
>サ行音とは
>タ行音とは
>ラ行音とは
>異常構音とは
>搬化・定着のための指導
>搬化・定着のための指導の方法
>自己修正力を育てるための指導
▼ ▼ ▼
【 私の場合 】
後から分かった事ですが、診断書に「軽度の構音障害」と記載されていました。
発症当初は、顔が歪み話すのも覚束ない状態でしたが、入院中のリハビリのお陰で大分話す事ができるようになってきました。
が、退院してから話す機会が減ると、入院時よりも何となく話づらくなって来た様に思います。
上記にあるように、山川さんを見習って「運動障害性構音障害:家庭でできること」を少しでもやらないと、と思う今日この頃でした。
仕事をしだすと難しいんだよね・・・。
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
高次脳機能障害
-
【 高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター) 】
- 高次脳機能障害を理解する >高次脳機能障害とは
- よくあるご質問 >全国の高次脳機能障害者数について
- 相談窓口(支援拠点機関一覧[都道府県分]) >高次脳機能障害支援拠点機関一覧(都道府県分)
- 医療について知りたい
- リハビリテーションについて知りたい >実施体制
- 福祉サービスについて知りたい
- 生活支援について知りたい >環境調整支援
- 就労支援について知りたい
- 知りたい!認知症のリハビリ・高次脳障害のリハビリ >認知症のリハビリ方法
- 高次能機能障害支援のご案内(名古屋市総合リハビリテーション事業団) >高次脳機能障害のある方へ
-
高次脳機能障害リハビリテーション講習会(福井県高次脳機能障害支援センター)
高次脳機能障害教室(福井県高次脳機能障害支援センター) - ハノイの塔(MTBI仲間の会) これは、注意機能障害と遂行機能障害のリハビリです。
- フラッシュ暗算:FLASH ANZAN フラッシュ暗算は、注意障害、記憶障害、視覚処理能力の回復のリハビリです。
-
高次脳機能障がい者 支援ガイド Q&Aから見る関わり方について(PDF)
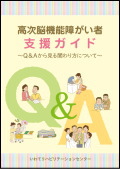
いわてリハビリテーションセンター
>高次脳機能障害とは -
高次脳機能障害とともに-ご家族の方へ(PDF)
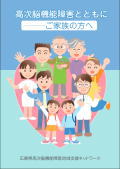
広島県立障害者リハビリテーションセンター
>高次脳機能障害とは -
高次脳機能障害~理解と支援のために~(PDF)
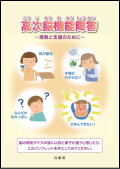
兵庫県総合リハビリテーションセンター
>高次脳機能障害とは? -
高次脳機能障害 明日の一歩のために 支援ガイド(PDF)

千葉県千葉リハビリテーションセンター
>高次脳機能障害って何? -
高次脳機能障害の理解と支援のために(PDF)

堺市立健康福祉プラザ(堺市高次脳機能障害支援拠点機関)
>よくある疑問・質問
> 高次脳機能障害診断基準
>主要症状の解説
> 記憶障害
> 注意障害
> 遂行機能障害
> 社会的行動障害
> 外傷性脳損傷後のMRI所見
>受傷・発症から社会参加までに関連するサービス
>高次脳機能障害の定義
>高次脳機能障害の症状
>高次脳機能障害の診断
>症状の経過
>家族の接し方
>職種ごとの訓練の具体的内容
>高次脳機能障害者に対する訓練の進め方
>高次脳機能障害の評価とは
>訓練の計画を立てる
>具体的な目標を決める
>訓練を行う際の留意点
>訓練に共通する考え方
>実際に標準的訓練プログラムを開始する場合
>生活・介護支援
>家族支援
>移動支援
【 リハビリ 】
>高次脳リハビリとは
>注意障害のリハ
>記憶障害のリハ
>半側空間無視のリハ
>構成障害・頭頂葉症状
>知的低下・全般低下
>高次行為障害のリハ
>前頭葉症状のリハ
>他の障害のリハ
>概要
>情報・資料
>高次脳機能障害関連情報
>注意機能障害では「続けられる力」を養います。
>遂行機能障害では「段取り」「手順」を覚える力を養います。
※リハビリの教材、グッズについては、
【 関わり方、対応 】
>Q&A集
>より良い生活を送るために
>高次脳機能障害の具体的な症状とその対応方法
>新しい生活を目指して
>高次脳機能障害の主な原因
>高次脳機能障害診断基準
>注意障害 症状 対応
>記憶障害 症状 対応
>遂行機能障害 症状 対応
>社会的行動障害 症状 対応
>社会復帰への基本的な流れ
>高次脳機能障害を支える制度
>就労支援の各種制度
>当事者・家族会のご案内
>こんなとき どうしたらいい?
>あなたはいま、どんなステージにいますか?
>高次脳機能障害とは
>高次脳機能障害に対するリハビリテーションについて
>高次脳機能障害に関わる社会保障制度
>社会復帰・社会参加に向けた流れ
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
再発を防ぐ&病診連携
- [88] 脳卒中の再発を防ぐ >ところで脳卒中ってどんな病気?
- [94] 上手にスムーズに治療を続けるために-脳卒中の病診連携を中心に- >生活習慣病はどう進むのか
- 脳卒中危険度チェック
>脳卒中の再発予防
1.原因となった病気の治療:危険因子の管理
2.生活習慣の改善
3.薬物療法:薬を飲んで血栓ができるのを防ぐ
4.手術
>定期的に検査を受ける
※退院後は、上記に注意して生活をしましょう!
>病診連携とは
>かかりつけ医と専門医
>紹介には二つのタイプ
>脳卒中の段階(ステージ)
>大切な医療連携・地域連携
>地域リハビリテーション
>地域連携パスとは
>退院後の生活のポイント
>再発を予防する
※定期的なチェックが再発を防ぎます。
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
高血圧と薬について
- 病気のついて:高血圧 1.高血圧について
- 高血圧の薬 >降圧薬の種類は?
(1)血圧とは何か
(2)最高血圧・最低血圧とは
(3)高血圧症とは
(4)高血圧症の種類
(5)高血圧症から起こる病気
2.日常生活の留意点について
(1)減塩について
(2)寒さについて
(3)入浴について
(4)排泄について
(5)十分な睡眠と休養について
(6)たばこについて
(7)お酒について
(8)肥満について
(9)運動や労作について
3.食事について
4.家庭で血圧を測定される方へ
(1)いつも同じ腕・姿勢・時間に測るようにしましょう。
(2)測るときは、きついシャツ等で腕の上部を締め付けないようにしましょう。
(3)血圧計は、腕と同じ高さのところにおいて測りましょう。
(4)血圧記録用紙の記入の仕方(例)
(5)血圧計は、定期的に使い始めと、その後、数年に1回の点検が必要です。
(6)高血圧の薬を飲まれている方へ
>副作用は?
>食事の影響は?
▼ ▼ ▼
【 私の場合 】
毎朝朝食後1回、以下の薬を飲んでいます。
・オルメテック錠20mg→オルメサルタンOD錠20mg > 血圧を上昇させる物質の働きを抑えて、血圧を下げます。
・アムロジピンOD錠5mg→2.5mg > 抹消の血管を拡張して血圧を下げる薬です。心臓へ酸素や栄養を供給している冠血管を拡張する薬です。
・ランソプラゾールOD錠15mg > 胃酸の分泌を強くおさえて、胃や十二指腸の潰瘍や食道の炎症などを改善する薬です。
※2017/5/15にリハビリ入院した時に、ランソプラゾールOD錠15mgが、ネキシウムカプセル20mg に変更になり、以降、この薬になりました。
(今まで一包化できていた物が、できないからと言う理由でしたが、少しでも薬代を高くしたいと言う病院の思惑のような?)
※2017/11/20より「オルメサルタンOD錠20mg」のジェネリックになりました。
※2018/12/01より血圧が2桁台に下がるようになったので「アムロジピンOD錠5mg」を止めて様子を見る事になりました。→2019/01/07より「アムロジピンOD錠2.5mg」にしました。
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
減塩食について
- 減塩食について >おいしい減塩食で、循環器病予防
※退院後の食事、特に塩分に注意しましょう!
>なぜ「減塩」が必要なのか?
>Q&A
>減塩に関連する動画(国循チャンネル)
▼ ▼ ▼
【 私の場合 】
(病院の減塩食より少ししょっぱめで、一般食よりは薄味[減塩]になっている感じの弁当です。)

※写真は標準で、170gのご飯とセットで約500~600kcalの弁当となってます。
介護減塩弁当は、野菜中心ですが、おかずが5つ(魚と肉と他3つ)付いているとてもバランスのとれた弁当となっており、ごはんが220g~270gで約750kcal~800kcalに設定しています。(特注と言っても、ただおかずとごはんを大盛りにしただけです。)
朝食は、主に食パンかロールパン3つと野菜ジュース180ml、魚肉ソーセージ1本(カルシウムが牛乳より多い物)、ヨーグルト200gを自分で用意して食べるようにしています。
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
痙縮(けいしゅく)と拘縮(こうしゅく)
-
病院を退院して介護保険を利用した施設でリハビリを受けると「拘縮(こうしゅく)」と言うことばをよく耳にします。
- 手足のつっぱり痙縮(けいしゅく)情報ガイド
- 痙縮:Wikipedia:ウィキペディア
- 痙縮とは?(痙縮の説明):第一三共株式会社
- 拘縮:Wikipedia:ウィキペディア
病院では「痙縮(けいしゅく)」は耳にしても「拘縮(こうしゅく)」はほとんど耳にしませんでした。
似たような言葉ですけど、いったい何が違うのでしょうか?
早い話が、「痙縮(けいしゅく)」は、筋肉のつっぱり で、「拘縮(こうしゅく)」は、関節の硬直 の事を言いますが、詳細は、下記をクリックしてください。
>脳卒中(脳血管障害)とは
>痙縮(けいしゅく)とは
>回復に必要なリハビリ
>痙縮の治療法
>治療費・公的支援
>ご家族の方へ
>患者さん・ご家族の体験談
>病医院検索
脳出血とは&その症状 |
リハビリ(理学・作業)
リハビリ(言語) |
高次脳機能障害 |
再発を防ぐ&病診連携
高血圧と薬について |
減塩食について |
痙縮と拘縮
最新脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)情報等
- 臨床研究情報
(治験情報)
●脳卒中で参加者募集中か一般募集中となっている臨床研究(治験)の情報が以下より参照できます。
臨床研究情報ポータルサイト
※「・・詳細を確認する」をクリックし内容及び、適格性(選択基準)をご確認の上、試験問い合わせ窓口担当者名へEmailあるいは、電話すると、参加の方法等を教えてもらえるはずです。
是非、トライして見て下さい。
最新医療
サイト本来の主旨(リハビリ)とは違いますが、最新医療についても掲載しておきます。
現実的な医療の現場では
★脳卒中の予防と治療:一般法人 先進医療推進機構(9:02のVTRありPCのみ)
●急性期脳梗塞に対するtPA静注療法
※4.5~8時間以内に行なわなければいけない治療
●急性期脳梗塞に対する脳血管内治療
●超急性期脳梗塞に対する血栓回収療法
※「聖マリアンナ医科大学 東横病院 脳卒中センター」の療法説明を引用しています。
将来的な医療は(再生医療治験)
●身近なクリニックでの再生医療が開始
▼ふくとみクリニック(大阪市都島区)
・再生治療の効果と可能性
・再生医療の診療の流れ
・治療費について
▼釧路孝仁会記念病院(北海道釧路市)
・脂肪由来幹細胞治療の特徴
・脂肪由来幹細胞による治療の流れ
・脂肪由来幹細胞治療の治療費について
・患者様の症例
▼デイクリニック天神(福岡市中央区)
・脳出血・脳梗塞後の後遺症の再生医療
▼BTRアーツ銀座クリニック(東京都港区)
・自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた脳血管障害治療
●札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所
・脳卒中の最新治療:先進医療推進機構(7:42のVTRありPCのみ)
・テルモ生命科学芸術財団の生命科学のDOKIDOKI研究室の
・再生医療治験のお知らせ:札幌医科大学付属病院 ※2016/10/01時点、脳梗塞の治験参加者募集中!
「第14回 骨髄幹細胞で脳梗塞を治療」(紙芝居)と
「脳梗塞や難治性の病気に役立つ研究を続けたい」(札幌医科大学 医学部附属フロンティア医学研究所 本望 修教授インタビュー) に詳しく説明されています。
※20日をめどに札幌医科大学付属病院へ転院して行なう治療(1ヶ月半経過した患者にも効果あり!)
●東北大学大学院医学系研究科
・Muse細胞 再生医療の可能性:先進医療推進機構(9:17のVTRありPCのみ)
・Muse細胞がもたらす医療革新‐動物モデルにおいて脳梗塞で失われた機能の回復に成功‐:東北大学大学院医学系研究科
※脳梗塞患者を対象としたMuse 細胞製品「CL2020」の探索的臨床試験を2018年9月中旬から開始 → 詳細はこちら
・生体に内在する多能性幹細胞Muse細胞を用いた次世代再生医療開拓への挑戦:東北大学大学院医学系研究科
●兵庫医科大学
・脳梗塞で死んだ細胞再生 兵庫医科大、定説覆す:神戸新聞
・多能性をもつ「iSC細胞」の実用化に向けた再生医療についての研究を開始:兵庫医科大学
・先端医学研究所 神経再生研究部門:兵庫医科大学
●サンバイオ株式会社
サンバイオの再生医療(再生細胞薬)
※現在は、募集している治験はありません。(2018/10/01)
脳梗塞のほか、外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、脊髄損傷及びアルツハイマー病等、既存の医療・医薬品では対処できない中枢神経系領域の疾患を対象としています。