脳出血を発症してから1-2年のリハビリとその時の症状を記録したものです。過去からどの程度回復したのかを比較して見てください。1年経過のスタートは、促痛反復療法(川平法)です。
発症後1-2年(維持期)
発症後1-2年(維持期)のスタートは、促通反復療法(川平法)実施病院に掲載されている群馬県の角田病院(つのだびょういん) へ行って促通反復法(川平法)を受ける事にしました。(2016/09/17~2016/10/19)
「川平法リハビリ合宿集中プログラム」による短期リハビリですが、どのように回復するかは、楽しみでもあり不安でもあります。
運転免許や介護保険の更新もあり群馬県での促通反復療法(川平法)が短期間となったため、次は、BMI療法を受けることにしました。
と言っても、BMI療法は、だれでも受けられる訳ではないので、まずは診察を受けてと言う事になります。
2016/10/19に群馬県から戻ってきて、翌日の2016/10/20には運転免許センターに行って更新手続きをして来ましたし、
2016/11/14には介護保険の認定員と面談をし、その足で慶應義塾大学病院へ行くためビジネスホテルに移動して、翌2016/11/15に慶應義塾大学病院で診察を受けました。(結構ハード!)
運転免許は、オートマ(AT)の限定付きながらも更新ができましたし、慶應義塾大学病院の方は、BMI療法が終了していましたが、類似の新たな研究がスタートしたことを知りましたので、即座にその研究への参加を申し込んで来ました。(研究への参加は、3,4ヶ月待ちの状態らしいです。)
後は、慶應義塾大学病院からの連絡待ちになりました。
2016/12/02には、介護保険の認定の結果が出て、予想通り「要支援1」になりました。(なので、今後のリハビリについてどうするか思案中です。ん~~~)
慶應義塾大学病院の方よりそろそろ連絡来る頃ではと思い、2017/02/15にボトックスの注射を打ちに近くの○○大学病院に行きました。
すると、2017/03/09の週1回のリハビリの日に、何と、右手小指がパー側に動くようになっているではありませんか!感動です!!
その後、4月になっても慶應義塾大学病院からは連絡が来ず、その代わりに東北大学病院で磁気刺激装置「Pathleader(パスリーダー)」による短期集中リハビリを行なっているとの情報をもらったので、直ぐに手続きをして2017/05/16から入院しての短期集中リハビリを行なうことにしました。
※「促通反復療法(川平法)や実施病院への手続き」については、![]() を参照してください。
を参照してください。
※「慶應義塾大学病院の最新療法・研究や参加手続き」については、![]() の慶應義塾大学を参照してください。
の慶應義塾大学を参照してください。
【 身体障害者2級(上肢2[重度],下肢4[中等度]) 】
【 介護保険:要支援1 】
| 日付 | リハビリ | 症状/実績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016/9/17 ~ 2016/10/19 |
「個別リハビリ」: [0]リラックス状態をつくる [1]肩関節の屈曲・伸展  [2]肘関節屈曲・伸展  [3]前腕回内・回外  [4]手関節  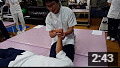 [5]手指  ※上記のトレーニング(手技)をIVES(アイビス)[随意運動介助型電気刺激装置](PCのみ)と併用することで相乗効果が得られます。 説明については、電気刺激療法をクリックしてください。 [6]上肢リーチング訓練装置 腕の曲げ伸ばしを装置が補佐しながら反復訓練をするリハビリで、私の場合5回位利用する機会がありましたが、15分間で最初250回位だったものが、5回目には500回位出来るようになってました。 装置の詳細については、タイトルリンクをクリックしてください。 「自主トレーニング」: ●振動療法(上肢・下肢) ボトックス注射を打った筋肉に振動を与えると効果的との事  振動の参考VTRです。 説明については、タイトルリンクをクリックしてください。 ●書籍「やさしい図解「川平法」歩行編」 [1]座っておじぎ [2]左右にゆらゆら [3]健足ひざ上げ [4]片手体重乗せ [5]足首つかみ1 [6]足首つかみ2 [7]おしり浮かし [8]立ち上がり※ [9]立位バランスをとる ●立ち上がり練習100回※ ●歩行練習(1階廊下) |
「手」は、据わった状態で手を上げると頭の高さまで上がるようになり、又、腕を横へ動かせるようになりました。 ただ、力を入れると肘が曲がって来るので、真っ直ぐのまま上へあげるのも横へ延ばすのもまだ無理です。 指は、テノデーシス作用を利用した1,2cmの開閉ができるようになり、具体的には、名刺やポケットティシュを掴んだり離したりができるようになりました。(6段階レベルの「3レベル」) 緊張(痙縮(けいしゅく))が強くなると指がグーになるので、コップを持つには、これを克服しなければなりません。 「足」は、期間中、川平法の歩行スタイルにするためにロフストランド杖に持ち替えた結果、麻痺足に負担が掛からない歩き方になりました。 T字杖に戻っても川平法の歩行スタイルになりました。 |
2016/9/8 促通反復療法(川平法)のリハビリがスタートするはずでしたが、パフォーマンスを上げるためボトックス注射を打ってから実施する事になりました。 ※促通反復療法(川平法)の詳細は、 を参照してください。 2016/9/17~ 17日にボトックス注射を打ち、19日よりいよいよ促通反復療法(川平法)の始まりです。 ※下部のエピソードを参照してください。 目標は、指が開くようになり、コップを持つことができるようになることです。 |
| 2016/10/20 ~ |
「リハビリ」: 週3回(月、水、金) [1]レッドロープを使用したストレッチを15分 [2]麻痺した腕の手首と肘をレッドロープでつってリラックスした状態でIVES(アイビス)稼動を15分 ※その他詳細メニューは、デイサービスの企業秘密との事! 「自主トレーニング」: ●書籍「やさしい図解「川平法」歩行編」 [1]座っておじぎ [2]左右にゆらゆら [3]健足ひざ上げ [4]片手体重乗せ [5]足首つかみ1 [6]足首つかみ2 [7]おしり浮かし [8]立ち上がり※ [9]立位バランスをとる ●立ち上がり練習100回※ |
「手」 上記の状態と変わらず。と言いたい所ですが、出歩くことが多くリハビリを受けていなかったせいなのか、浮腫むことが多くなってしまった。 後、痙縮(けいしゅく)が強くなりグーになることが多くなったような気がする。 「足」 上記の状態とほぼ変わらないが、歩き方を変えたせいか、麻痺足(右足)の付け根が痛くなるようになった。 又、健足側(左足)も直ぐに疲れるようになった?(単に歩きの不足かも?) |
2016/10/20 自動車の運転免許センターへ行き、更新手続きをしてきました。 ※更新手続きは、 の自動車運転免許の更新手続きを参照してください。 2016/11/14,15 慶應義塾大学病院の診察を受け、新しい研究への参加手続きをして来ました。 ※詳細は、 の慶應義塾大学を参照してください。 |
| 2016/12/01 ~ |
「リハビリ」: 週1回(木) [1]レッドロープを使用したストレッチを15分 [2]麻痺した腕の手首と肘をレッドロープでつってリラックスした状態でIVES(アイビス)稼動を15分 ※その他詳細メニューは、デイサービスの企業秘密との事! 「自主トレーニング」: ●書籍「やさしい図解「川平法」歩行編」 [1]座っておじぎ [2]左右にゆらゆら [3]健足ひざ上げ [4]片手体重乗せ [5]足首つかみ1 [6]足首つかみ2 [7]おしり浮かし [8]立ち上がり※ [9]立位バランスをとる ●立ち上がり練習100回※ |
「手」 ほとんど変化なし(週1回では当然です。) でしたが、2017/02/15にボトックス注射をを打ってから3週間位が経った 2017/03/09(木)にいつものようにリハビリをしていたら、麻痺した小指がパー側にピクピクと1cm位動きました。びっくりです。 「足」 ほとんど変化なし(週1回では当然です。) ※障害年金のため診断書を取って初めて自分の病状を知りました。 ●軽度構音障害、中等度運動性失語、右不全片麻痺 ●右片麻痺は、上肢 2(重度)、手指 2(重度)、下肢 4(中等度)、感覚障害軽度鈍麻 発症から1年半後ではなく、もっと早くに知っておけば良かった! |
※ここから要支援1です。 週1回のリハビリでは、話になりません。 なので、歯医者に行きつつ、当分の間、仕事の再開準備をしようと思ってます。 慶應義塾大学病院の新研究参加待ちです。 2017/02/15 ボトックス注射を打ち、慶應義塾大学病院からの連絡を待ってましたが、2017/03/01に確認した所、まだ不確定で4月なるか5月になるか分からないとの事。 ※下部のエピソードを参照してください。 2017/05/01 2017/04/02に発症後1年半を向え障害年金の申請ができるので、申請書類を一式揃え役所へ行きました。 ※障害年金については、 の障害年金を参照してください。 |
| 2017/05/16 ~ 2017/06/30 |
「リハビリ」: [1]磁気刺激装置「Pathleader(パスリーダー)」を肩、肘、指に当て刺激する(30分) [2]スパイダースプリントを麻痺指にはめてグー・パーの繰り返しと積み木の移動と重ねの分離運動(30分) 「自主トレーニング(柔軟体操)」: ●手を組んでばんざい ●手を組んだ手を床につける ●背中に手をまわす ●組んだ手を頭の後にまわす ●スパイダースプリントによる指のグー・パー ●指の筋肉への刺激(指1本づつ) ●マッサージ器(スライブ)による振動 |
「手」 [1]麻痺側の腕を上げてゆっくりと頭の後まで持って行ける様になった。 [2]立った状態で麻痺した手を尻まで持って行こうとするが半分位までしか行かない。 [3]指(中指、人差し指)が寝ているとパー側に1cm位動くようになったが、起き上がると動かない。 「足」 足にも1箇所だけにボトックス注射を打ちましたが、ほとんど変化なしです。 |
2017/03/09の小指がパー側に動いたのを受けての短期集中リハビリでしたが、他の指が反応してくれて成果が上がったので良かったです。 2017/05/16~06/30 入院しての短期集中リハビリ 2017/05/25 「指」が緩むようにボトックス注射を打ちました。 ※下部のエピソードを参照してください。 |
▼ ▼ ▼
【 エピソード(episode) 】
|
「促通反復療法(川平法)を始めて受けて」: 2016/9/17に初めてボトックス注射を15箇所(手:7箇所、足:8箇所)打って、2016/10/19まで促通反復療法(川平法)を受けたのですが、結論から言うと「指は動きませんでした。」 原因は、ボトックス注射を15箇所も打ち、容量を分散させたので効き目が薄れた事(次のボトックス注射を打って分かった事です。)と介護保険ではリハビリ時間が医療保険の半分になってしまって反復回数が少なかった事にあるように思います。 それと、私の手が「重度」の麻痺で、筋緊張が強かった事も原因と思われます。 しかし、促通反復療法(川平法)は、従来の自力で行うリハビリとは違い、他力(イメージは自力)で反復してくれるので、あまり疲れずに反復回数を多くでき、それにより何か動くようになるのでは?と思わせる物があります。 軽度・中度の麻痺者対象か? もう一度試してみたいです。 そう言えば、担当理学療法士が、リハビリもロボットがやるようになるのがそう遠くない日に来るような事を言ってました。(ただ、患者からすれば早く来て欲しいのですが、何やら抵抗勢力が居るみたいで・・・。) 私の住んでいる都道府県の病院・施設では、促通反復療法(川平法)を実施しておらず、そこの作業・理学療法士も自力でやらせるリハビリだけでなく、もっと患者側に立って反復回数を多くする工夫を考えて欲しいなあと思っているんですが・・・。 「ボトックス注射」: 2016/9/17: 何も分からず、ドクター任せでボトックス注射を15箇所(手:7箇所、足:8箇所)打ちましたが、あまり、緩んだようには思えませんでした。 2017/2/15: 慶應義塾大学病院の新研究への参加のために、「手」中心に、特に指が動くようにボトックス注射を7箇所打ちました。が、慶應義塾大学病院から連絡が来ません。 3/9にデイサービスへ行き何気なくリハビリをやっていると、右手の小指がパー側にピクピクと1cm位動きました。 ボトックス注射だけで、大したリハビリもやっていないのに・・・。ほんと、びっくりです! ※ボトックス注射って、ピンポイントに緩めたい所へ集中して打たないと効き目がないんだ、と実感しました。 2017/5/25: 1ヶ月集中リハビリで入院してのボトックス注射でしたが、前回とは、少々打つ場所を変えて、主要3指(親指、人差し指、中指)に重点を置いて7箇所打ってもらいました。 ※私の場合、ボトックス注射を打ってから3週間目にピークを向え、1ヶ月位効果が見込めるが、そこから急に効果が無くなって行く感じになります。 一度動いた指は、ボトックス注射の効果が無くなっても持続し、リラックスしている時にはちゃんと動くが、筋緊張が高い時は動きません。 脳波は出ているが弱く、それを強くし、筋緊張が高い時でもパー側に動くようにするのが課題です。 |
最新脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)情報等
- 臨床研究情報
(治験情報)
●脳卒中で参加者募集中か一般募集中となっている臨床研究(治験)の情報が以下より参照できます。
臨床研究情報ポータルサイト
※「・・詳細を確認する」をクリックし内容及び、適格性(選択基準)をご確認の上、試験問い合わせ窓口担当者名へEmailあるいは、電話すると、参加の方法等を教えてもらえるはずです。
是非、トライして見て下さい。
最新医療
サイト本来の主旨(リハビリ)とは違いますが、最新医療についても掲載しておきます。
現実的な医療の現場では
★脳卒中の予防と治療:一般法人 先進医療推進機構(9:02のVTRありPCのみ)
●急性期脳梗塞に対するtPA静注療法
※4.5~8時間以内に行なわなければいけない治療
●急性期脳梗塞に対する脳血管内治療
●超急性期脳梗塞に対する血栓回収療法
※「聖マリアンナ医科大学 東横病院 脳卒中センター」の療法説明を引用しています。
将来的な医療は(再生医療治験)
●身近なクリニックでの再生医療が開始
▼ふくとみクリニック(大阪市都島区)
・再生治療の効果と可能性
・再生医療の診療の流れ
・治療費について
▼釧路孝仁会記念病院(北海道釧路市)
・脂肪由来幹細胞治療の特徴
・脂肪由来幹細胞による治療の流れ
・脂肪由来幹細胞治療の治療費について
・患者様の症例
▼デイクリニック天神(福岡市中央区)
・脳出血・脳梗塞後の後遺症の再生医療
▼BTRアーツ銀座クリニック(東京都港区)
・自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた脳血管障害治療
●札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所
・脳卒中の最新治療:先進医療推進機構(7:42のVTRありPCのみ)
・テルモ生命科学芸術財団の生命科学のDOKIDOKI研究室の
・再生医療治験のお知らせ:札幌医科大学付属病院 ※2016/10/01時点、脳梗塞の治験参加者募集中!
「第14回 骨髄幹細胞で脳梗塞を治療」(紙芝居)と
「脳梗塞や難治性の病気に役立つ研究を続けたい」(札幌医科大学 医学部附属フロンティア医学研究所 本望 修教授インタビュー) に詳しく説明されています。
※20日をめどに札幌医科大学付属病院へ転院して行なう治療(1ヶ月半経過した患者にも効果あり!)
●東北大学大学院医学系研究科
・Muse細胞 再生医療の可能性:先進医療推進機構(9:17のVTRありPCのみ)
・Muse細胞がもたらす医療革新‐動物モデルにおいて脳梗塞で失われた機能の回復に成功‐:東北大学大学院医学系研究科
※脳梗塞患者を対象としたMuse 細胞製品「CL2020」の探索的臨床試験を2018年9月中旬から開始 → 詳細はこちら
・生体に内在する多能性幹細胞Muse細胞を用いた次世代再生医療開拓への挑戦:東北大学大学院医学系研究科
●兵庫医科大学
・脳梗塞で死んだ細胞再生 兵庫医科大、定説覆す:神戸新聞
・多能性をもつ「iSC細胞」の実用化に向けた再生医療についての研究を開始:兵庫医科大学
・先端医学研究所 神経再生研究部門:兵庫医科大学
●サンバイオ株式会社
サンバイオの再生医療(再生細胞薬)
※現在は、募集している治験はありません。(2018/10/01)
脳梗塞のほか、外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、脊髄損傷及びアルツハイマー病等、既存の医療・医薬品では対処できない中枢神経系領域の疾患を対象としています。
脳出血(脳卒中)の基礎知識
脳出血のリハビリだけでなく、脳出血、広くは脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)に関する基礎的な知識も押さえて置きましょう。
病気の症状・治療やリハビリのことだけでなく、退院後の再発防止のことや薬、食事のことまで載ってますので、一度ご一読するよう強くお勧めします。
- 脳出血とは&その症状 >脳卒中|病気について
- リハビリ(理学・作業) >脳卒中のリハビリ・・
- リハビリ(言語) >脳卒中と言葉の障害
- 高次脳機能障害
>脳卒中が起こったら
>脳卒中にも色々あります
>続・脳卒中のリハビリ・・
>脳卒中の言語リハビリ・・
- 再発を防ぐ&病診連携 >脳卒中の再発を防ぐ
- 高血圧の薬について >病気のついて:高血圧
- 減塩食について
- 痙縮(けいしゅく)と
拘縮(こうしゅく)
>手足のつっぱり痙縮情報ガイド
>上手にスムーズに治療を・・
>痙縮とは:ウィキペディア
>拘縮とは:ウィキペディア